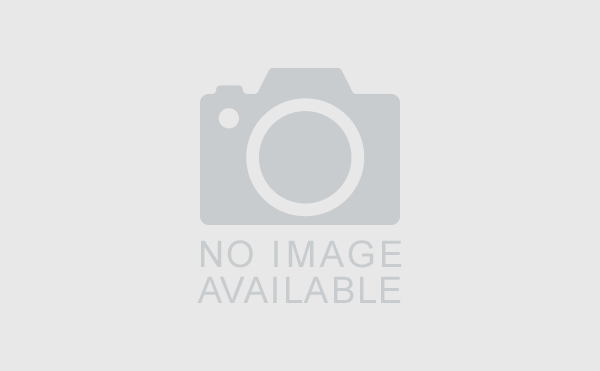🌾 10月17日は「貯蓄の日」──収穫に感謝し、未来を育む日
今日は「貯蓄の日」。
五穀豊穣に感謝する”神嘗祭(かんなめさい)”にちなんで制定されたこの日は、勤労の実りに感謝しながら、未来への備えについて考えるのにぴったりな日です。
”貯める”ことの意味をもう一度見つめ直し、
”そだてる”視点でこれからの資産づくりを考えてみませんか?
🏦 「貯蓄の日」の由来
毎年10月17日は「貯蓄の日」。
戦後7年目となる1952年に貯蓄増強中央委員会(現:金融広報中央委員会)が制定したそうです。
委員会の発足を記念するとともに、勤労の実りを大切にし、貯蓄への関心を高めることを目的としています。
日付は、宮中祭祀のひとつ「神嘗祭(かんなめさい)」に由来します。
神嘗祭は、天皇がその年の新米を伊勢神宮にお供えし、五穀豊穣を感謝する祭典。
この「感謝」と「実り」の精神を、日々の暮らしの中でお金との向き合い方に重ねたのが「貯蓄の日」なのです。
この日を中心に、優良こども銀行や貯蓄功労者の表彰など、貯蓄の大切さを広める活動が行われてきました。
💴 「貯蓄」とは何か──”ためる”の本当の意味
「貯蓄(ちょちく)」とは、文字通り“蓄える”こと。
経済学的にはさまざまな定義がありますが、一般的には現金・預金・投資・年金・保険などを通じて資産を蓄える行為を指します。
「貯蓄」とは単にお金を寝かせることではなく、”将来の安心や豊かさをつくるための「心の備え」”と言っても良いのではないでしょうか?
📊 J-FLECの調査に見るリアルな家計感覚
J-FLEC(一般社団法人金融教育推進協会)が実施した「家計の金融行動に関する世論調査」では、次のような結果が示されています。

平均値に比べると「うちは少ないな…」と感じる方もいるかもしれません。
ですが、ここで注目したいのが「中央値」です。
🔍 「平均値」よりも「中央値」に目を向けよう
平均値は、一部の高額資産を持つ世帯が全体を押し上げてしまう傾向があります。一方で「中央値」は、すべての世帯を並べたときの真ん中の数字。
より現実的で、私たちの生活実感に近い数字です。
中央値を見ると、「思っていたより、うちも人並みかもしれない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
大切なのは、焦ることではなく、自分なりのペースで備えること。
そして、その一歩を今日のような「貯蓄の日」に思い出すことが、未来への力になります。
🌱 「ためる」から「そだてる」へ
かつての「貯蓄」は”守り”のための行動でした。
でもこれからは、”自分と家族の未来を育てるための「そだてる貯蓄」”へ。
たとえば
つみたてNISAなどで小さく長く投資を続ける
家計を「削る」より「活かす」視点で見直す
家族と将来の夢を語る
そんな小さな行動が、”ファイナンシャル・ウェルビーイング”につながります。
✨ おわりに:感謝と備えが、豊かさをつくる
神嘗祭が「自然の恵み」への感謝を示すように、
貯蓄の日は「これまでの自分の努力」や「家族の支え」への感謝を思い出す日。
お金をためることは、心を整えることでもあります。
感謝の気持ちを持って今日から少しずつ──
それが、”お金と心の両面での豊かさ=ファイナンシャル・ウェルビーイング”への第一歩です。
🕊️ ”今日の小さな備え”が、明日の安心に!
百壽総合研究所280-x-60-px.png)